自治体は、「公共政策マーケティング」と「政策形成」のバランス発想を持たないと地域創生やEBMPの実現が困難な三つの理由。
理解、EBPMに悩む-683x1024.png)
理由1:作り手、供給サイドの理屈である「政策形成」だけでは顧客(県民、市民、町民など)の視点が希薄。
従来からの政策は顧客側の視点は弱いと、私たちは考えています。なぜなら従来からの政策は作る側の視点が中心で、その思考の中には顧客理解や顧客の使用などの視点はほとんど反映されていないからです。
別の表現をすると政策形成は作り手の視点、供給サイドの理屈であり、使い手側の視点、すなわち顧客(市民)、需要サイドの理屈が希薄なのだと私たちは考えます。
今ほど顧客(市民)の多様性が自治体経営に影響していることはありません。また、需要と供給はバランスされなければなりません。
したがって、供給サイドの理屈である政策と、需要サイドの理屈のバランスが必要なのです。これが公共政策マーケティングであると私たちは主張しています。
多くのところで誤解があるのですが、「公共政策マーケティング=地域産品の売り方」の認識があります。もちろんどのような定義づけでも良いのですが、これでは政策に対峙できる需要者サイドの理屈にはなり得ません。売り方ももちろん包含しますが、もう少し大きな政策と同等でバランスできる上位概念が私たちの主張する公共政策マーケティングです。
理由2:顧客理解からアプローチまでの統合的思考がないために、具体的活動に落とし込めない。
最近はEBPM流行りで以前からあったロジックモデルを利用して、具体的に政策や事業の流れを捉えようとしているのは良いことです。
ただ、そのスタンスは作り手の視点です。ロジックモデルについてはまた別に解説しますが、あくまでも供給サイドの理屈で事業の流れをEBPMの論調の中では測定目的で使用しているに過ぎません。
経営学でMichael E. Porterが言うところのバリュー・チェーン(Value Chain)的な「顧客の価値連鎖」の視点がないのです。
さらには具体的に顧客(市民)との接点においては政策は沈黙します。したがって顧客サイドの視点が少ないと言えます。
したがってマーケティングのSTPから4Pまでの統合的(戦略的)アプローチを持たない限り、供給サイドの理屈だけに偏ります。多くの自治体で必要に迫られている「顧客(市民)理解」の具体的アプローチ方法は需要サイドの理屈、すなわち公共政策マーケティングなのです。
理由3:地域ブランディングや「ゆるキャラ」、最近はナッジ(nudge)などバラバラで実施され、統合的アプローチができない。
先ほどらい私たちが主張している需要サイドの理屈、すなわち顧客(市民)の理解と具体的アプローチ方法いついて、各自治体が何もしなかったわけではありません。ただそれぞれの手法や知見、ノウハウを単体で投入している場合が多く、全体としての成果に結びついていないようです。
流行り廃りに振り回されている感すらあります。
ゆるキャラは多産多死の憂き目に遭い、地域ブランディングは特産品頼み。そしてキャッチコピーを変えただけのナッジ。
「ゆるキャラ」、多産多死の憂き目に遭う。
先ほど述べた「理由3」ですが、かなり以前から発生しています。
その代表格が「ゆるキャラ」です。目に見えるのでインパクトがありますし、それなりに訴求力があります。本当は政策と関連づけなければ成果は希薄ですが、そんなものお構いなしに産み続けられました。
今の自治体DXとよく似ています。
本来は公共政策マーケティングの4Pの内のPromotion / Communication の一つの地域ブランディングのそのまた一つの表現方法としてのゆるキャラなのですが、そんなことはお構いなしで産み続けられました。
「とりあえずみんなやってるし、なんとかなんじゃない?」
挑戦するのはいいことなのですが、何も裏付けがないのは挑戦ではありません。単なる博打ですね。全くもって今の自治体DXと同じです。
現在自治体関連のゆるキャラは全国に4000頭を超えるとされています。でも果たして適切にケアされて育成は目指されているのでしょうか?
その多くは飼育環境と育成(すなわち公共政策マーケティング)の考えがないままに放置されています。
これが私たちの言う、「ゆるキャラ、多産多死」です。
「地域の特産品」頼みの地域ブランディングで良いのでしょうか。
安倍政権下の2014年に地方(地域)創生が叫ばれてから結構経ちましたが、何か大きな成果があったように感じられないのは、私だけでしょうか?
幾つか動きがあったようですし、石破政権において少し注目されたようですが、その中心は「地域の特産品」頼みに感じられます。
ここでも出てくるのは、知見やパッケージの部分的な導入です。
地方(地域)創生として地域ブランディングを考えることは良いことです。しかし、目にみえるゆるキャラ、ネーミングやデザイン、挙げ句の果てには「地域特産品」頼みでは、本当の意味で地方(地域)創生は難しいでしょう。
ここでも多くの自治体で、公共政策マーケティングの議論はなされていません。手っ取り早く目に見える何か、すなわち、ゆるキャラ、特産品でなんとかしようとしているのです。
一時的には話題になるかもしれませんが、それは政策とは呼べません。
小手先のナッジ。
現在自治体では、行動経済学、ナッジの研修も盛んです。私たちもよく行動経済学、ナッジの研修のオファーをいただきます。使えるものはなんでも使えば良いのですが、名前だけに振り回されるのも注意しなければなりません。
ナッジでどこどこの自治体で住民の医療検診参加が〇〇%向上した、を学び使おうとするのは大切ですが、公共政策マーケティングのSTPと4Pの基盤は持っていて欲しいものです。
そして前提となる顧客(市民)プロファイリング起因の顧客ストーリーを描いて統合力として運用していただきたいのです。
でなければ当たったとされるキーワードをコピペして使うだけで「ナッジ完了!」。さて、全くユニークな別の自治体における再現性は如何に?
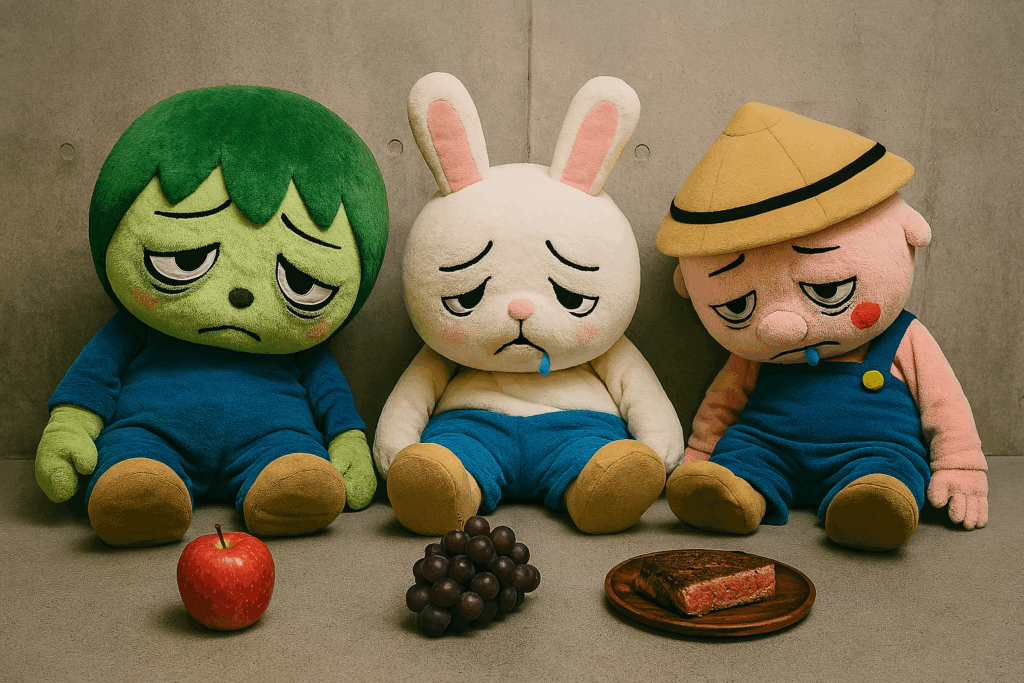
顧客(市民)理解が基盤にある統合された思考、公共政策マーケティングが必要。
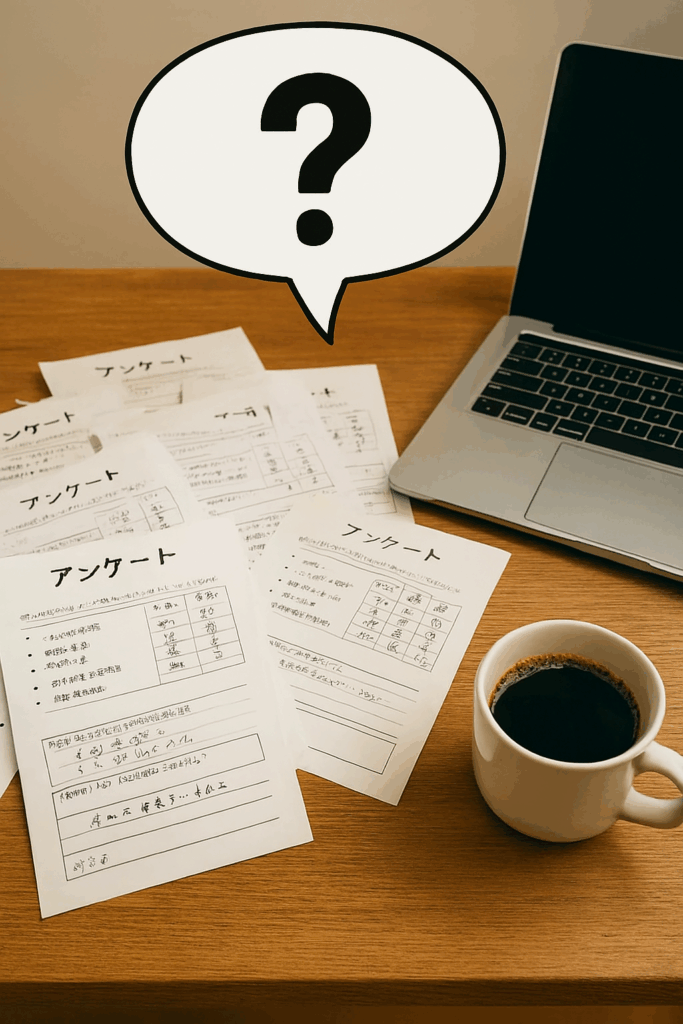
唐突に挿入される「市民ニーズ調査アンケート」では、わからない市民。
公共政策マーケティングと政策とのバランスと統合が重要な理由は、ズバリ顧客(市民)理解の上での政策形成を実現するためです。
私たちが声高に叫ぶ前にも、顧客(市民)理解の取り組みがなかったわではありません。例えばよくやられていたのが「市民ニーズ調査」です。
元々従来の政策形成には、市民理解、ニーズ理解は言葉の上では出てきますが、その具体的手法と戦略が組み込まれていたわけではありません。
供給サイドの理屈だけで良かった時代から顧客(市民)理解が必要になり始め、市民ニーズと政策とのギャップが著しくなり多くの批判に晒され始めた時、唐突に「市民ニーズ調査」が現れました。
顧客(市民)、需要サイドの統合力が必要なのです。
多くのところで「調査すれば、市民がわかる」と市民ニーズ調査なるものが実施され、多くのレポートが作成されましたが成果はどうだったのでしょうか?
「とにかく調べれば、何かわかる」。本当でしょうか?
これはあくまでも提供側、作り手、供給側の理屈です。顧客(市民)サイドの理屈なしに作られた調査、アンケートの質問項目、これらは果たして適切なのでしょうか?
こういった調査の土台を崩さないためにも公共政策マーケティング基盤の政策形成が重要であると私たちは主張します。
